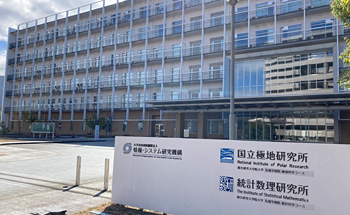AIのビジネス活用を成功させるために
4回にわたりマーケティング領域でのAI活用の可能性と課題について私見を述べてきたが、これで最後となる。最後は、AIのビジネス活用を成功させるために不可欠なことを述べさせていただきたいと思う。

繰り返される新技術への過度な期待
テクノロジーの将来性を評価するガートナーの有名なハイプカーブでは、ディープラーニングは2018年に「過度な期待のピーク期」を迎え、今後幻滅気に入っていくことを予言している。実際、我々がこのようなテクノロジーのバズワードに触れることは初めてではない。ここ数年で言えば、VRや暗号通貨などが世界を一変させる技術として、多くのメディアでもてはやされた。しかし、VR元年と呼ばれた2016年から現在までの対応端末普及の遅さ、暗号通貨の取引所のハッキング事件やビットコインの暴落などを見れば、それらが現在は幻滅期に入っていると評価されていることも納得感があるだろう。
かつてデータマイニングやビッグデータといったキーワードが流行っていたときも、現在の人工知能と同じような文脈でビジネスの競争優位を根底から変えてしまうと期待されていた。しかし、データが大量に集められたからと言って、直ちに意味のあるインサイトが見つけられるかは自明ではないし、事業収益性を高めるには必ずビジネスモデルの転換などの痛みも伴うような変革が求められる。コストをかけてビッグデータを収集し分析したものの、期待したような結果を導き出せず、ROIが見合わないとして終了してしまったプロジェクトも多い。その結果、今ではデータマイニングという言葉は死語となり、ビッグデータを担いでいた人もすっかり鳴りを潜めて、彼らの多くがその舌の根も乾かぬうちに今度は人工知能がビジネスを変えると声高に主張している。
アドテク(Ad Tech)やマーテック(Marketing Tech)と呼ばれるインターネット業界の一部、またIT活用を強みとするようなコンサルティング業界では、昔からCRMやOne-to-Oneなどのバズワードによって大企業クライアントからの新規の需要を生み出しては、その投資に見合った結果が得られずにフェードアウトするという焼き畑を繰り返してきた。
もちろん失敗から得られる学びもあるはずで、果敢に新しい技術の活用に挑戦すること自体を否定するべきではない。しかしながら、クライアント側も「失敗」と定義してしまうと担当者自らの社内評価が下がるため、効果が数%アップなどの小さな成果(それが統計的に有意かどうか、再現性があるのかどうか、怪しいレベルであっても)を「成功」と定義しているケースもある。ただし、その取り組みが継続していない背景には、投資に見合うほどの成果ではなかったという事実がある。
そして、失敗の本質を振り返る機会を失ったまま、ちょうどよいタイミングで次のバズワードがどこからともなくやってくるのである。
日本におけるAIのビジネス活用の現状
では、ディープラーニングをきっかけとする現在のAIブームもこれまでのバズワードと同様に、ガートナーのハイプカーブが示唆するような幻滅期へと突入していくのだろうか。
あるAIスタートアップ企業の役員が公開イベントでこのように発言していたことがあった。大企業から持ちかけられる案件の中には、ディープラーニングなどの最新のテクノロジーを利用しなくても、昔からある機械学習アルゴリズムの組み合わせで十分解決できるものも多いそうだ。それにも関わらず、なぜ大企業はこのスタートアップと協業をしたがるのか。それは、古い枯れた技術から最先端の学術研究まで全てをカバーした専門家集団から、“この技術で良いんだ”というお墨付きが欲しいという大企業担当者の心理があるらしい。
また、私が別のAIスタートアップ企業から同社テクノロジーの提案を受けたときには、このような説明があった。ディープラーニングによる顔認識を活用して店内の人の動線を可視化するという技術を開発したが、人の顔画像はプライバシー保護のガイドラインに準拠する必要あり、大企業に導入する際には当該技術を使わないことも多いそうだ。というのも、ガイドラインではホームページや店内掲示などで消費者への告知を徹底しなければならず、大企業において部署を超えた関係者の合意を取るという骨の折れる業務にコミットする担当者が実は少ないのだ。結果、個人を識別せずに匿名化された状態で動線を計測するなら、昔からあるレーザー・レーダー方式で十分ということになる。
これらの発言を聞いたときに、私は日本の大企業をクライアントとした仕事をしてきた経験から深い納得感を得るとともに、先述の通りかつてのバズワードがその失敗の本質を振り返らずに現れては消えていくのと似たような状況がそこにはあるなと、ある種の既視感を持った。いずれのスタートアップもディープラーニングを始めとした最先端の人工知能技術に強みを持ち、企業価値も高く評価されている。しかし、大企業との連携、そしてビジネスへの応用という意味では、その技術力を十分には活かせていないようだ。
どちらの事例も最新のテクノロジーが現場で活用されているわけではなく、昔からある技術の焼き直しに過ぎない。しかし、それを人工知能という便利な言葉でラベリングすることによって、大企業担当者は何か新しいことをやっている気になることができる。それでもビジネスの重要な課題を解決し、事業収益に貢献しているのであれば大変望ましいことだが、昔からある技術の組み合わせで解決可能なら、なぜ今まで取り組んでいなかったのだろうか。それは解決したところで事業収益に貢献するほどの大きな課題ではないのかもしれない。
AIのビジネス活用を成功させるために
本コラムでは、ディープラーニング登場によって再び注目を集める人工知能について、マーケティング領域に活かしていく上での課題を整理させていただいた。また、これらの論点はマーケティングにとどまるものではなく、他のビジネス領域にも当てはまると思う。
リーガルテックと呼ばれる法律関係のスタートアップの世界では人工知能によるパラリーガル業務の代替が始まっている。金融系のスタートアップであるフィンテックでは資金運用などの投資意思決定を人工知能に任せるというサービスも生まれている。ヘルスケアではMRIなどの画像診断が医師から人工知能に置き換わりつつある。これらの業界では、確かにそれぞれのビジネスにおける大きな課題に着目して、そこに多くの資金と優秀な人材を投下して人工知能が開発されている。
しかしながら、国内の広告やリテールなどを含むマーケティング領域では、メディアで取り上げられているAI活用事例もバズワード的なものが多く、本質的なビジネス課題の解決に取り組んでいるものは少ない。
一方、Amazonやアリババなど米中の先進企業はディープラーニングを活用した消費者体験の変革に積極的に取り組んでいる。Amazon Goなど単体でのROIは赤字だと思われるが、長期的には彼らの競争優位に直結すると確信して、投資を行っているに違いない。そこにあるのは、短期志向で人間の仕事を置き換えると言ったコスト削減ではなく、徹底したユーザー体験のパーソナライズ化という、従来の人間ではできなかったレベルのサービスを実現するためだろう。
日本の企業がAI活用を成功させるためには最近の流行として取り組むのではなく、自社の最大の課題を解決するぐらいの高い目標設定と、それに基づく大胆な投資の意思決定が不可欠だ。その上で、私が本稿で指摘させていただいた論点が、読者の皆様のプロジェクト成功の一助となれば幸いである。

MINO COMPANY 代表
慶應義塾大学総合政策学部卒。 調査会社にてキャリアをスタート。その後、コンテンツ投資会社を経て2007年に独立。さまざまなプロジェクトに参画しながら、2011年にGoogle入社。同社ではエンジニアや統計専門家を含むグローバルチームと共に広告効果測定プロダクトの開発、およびAPAC・日本国内における普及活動に従事。アドテクノロジーを活用した実験計画、多次元時系列データから因果を推論するベイジアンモデリング、深層学習や機械学習を使ったオンラインログデータの解析など、最先端のマーケティング・サイエンスのプロジェクトを主導。2018年末にコンサルティングおよび新規事業開発・投資事業を行うMINO COMPANY(正式名称:MINO合同会社)を設立。